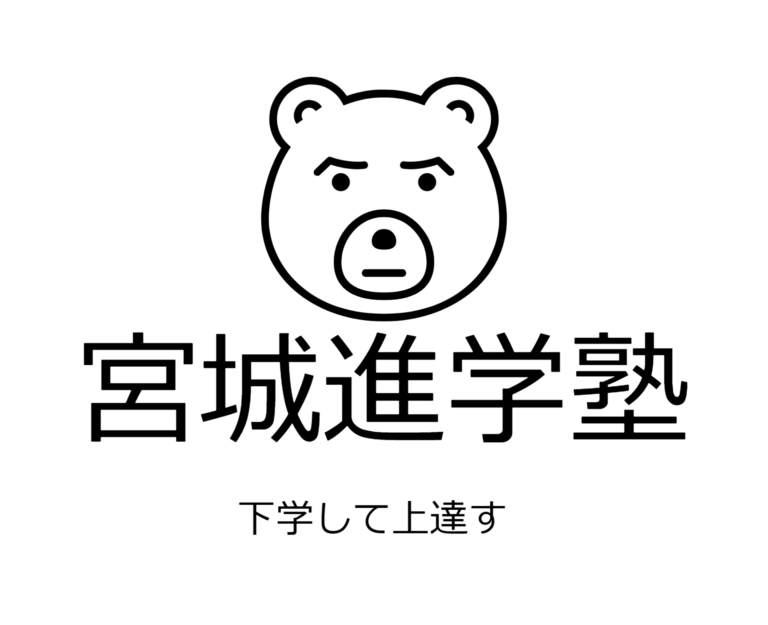今回は適性検査Ⅱについて記しておこうと思います。適性検査Ⅱは出題される教科としては算数と理科ですね。いわゆる理系科目です。今回は従来の問題と比べると文章で解答する問題が多かったです。なかなかできたという自信を持てた子は少なかったのではないでしょうか。塾生に聞いてもできた自信はなかったようです。
課題1 算数分野
問の数は1~4までと昨年と比べて1つ減っていますがでしたが問3と問4が小問が2つずつあったので合計では1つ増えていました。昨年は問1~3は答えが計算をして求めるような問題でしたが、今年は問2から説明を書かないといけない問題でした。データを分析して答えるという今後の大学入試を意識した問題だったと思います。
今回の課題1は共通テストのように穴抜きになっているところを埋める問題ばかりでした。この点は今までの問題と比べて大きく異なっていました。理系の問題でもしっかりと問題文の会話文を読み取れなければ何を答えないといけないかわからなくなっていました。
問4は分配法則を使って穴抜きの箇所に当てはまるように式を変形させる問題でした。高校生のマーク模試ではよくある形式でしたが、今までの適性検査ではあまり見られない問題でしたね。また、式の意味を説明させる問題もあったので、普段から途中式を書いて考えていないとうまく答えることはできなかったのではないでしょうか。全体的に単純な計算や文章題などはほとんどなかったように思えます。
課題2 理科分野
今年は天体の月と物質の状態変化に関する問題がだされていました。問題数は昨年と変化はありませんでした。記述解答の数は昨年より1つ減って4問でしたが、難易度は大きな変化はなかったと思います。
課題3 算数分野
差がつくところですね。50分という試験時間のなかで全て解答するのは難しいですが、どれだけできるところを拾えるかがカギになってきます。問の数は1~8と昨年より2問増加していますが、小問に分けられているところは少なかったので合計問題数は1問増加でした。
課題3も課題1と同様に単純な文章問題より記述解答が増えていました。問1~問5まででどれだけ得点できたかが重要だったと思います。問6~8は通年通りの解くのに時間がかかる問題でした。特に問7は2022年度の共通テスト数学2Bのの数列のような動いたり止まったりするような問題でした。このラスト3問はどれか1問を解くのが限界だったのではないでしょうか。
総合的には聞かれる難易度は昨年と大きく変わりはなかったと思います。いわゆる受験算数のような特殊な文章題もほとんど出ていませんでした。しかし、記述解答が大幅に増えており、解答に合わせて式を変形させる問題。式の意味を答える問題などは、普段からしっかりと練習しておかないと難しかったと思います。今後はこのような形式でいくのか再び計算量を増やしていくのかはここ何年かの問題見た限りでは過渡期といったところでしょうか。